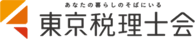会社設立日はいつが良い?決め方や節税につながるちょっとしたコツを紹介!

会社設立日として登録されるのは、法務局へ会社設立の登記申請を行った日です。自身でタイミングの調整が可能なため、縁起の良い日や特別な日と会社設立日を合わせるケースは多くみられます。
また、会社設立日について、節税につながるちょっとしたコツもあります。会社設立日は設立後の変更ができないため、会社設立日が会社経営に与える影響を知っておくことが大切です。
今回は会社設立日の決め方や注意点、節税につながるちょっとしたコツを紹介します。
会社設立日はいつになる?
最初に紹介したように、会社設立日として登録されるのは法務局へ登記申請を行った日です。法務局での手続きが完了した日ではありません。
法務局へ登記申請をする日を調整すれば、ご自身の希望する日を会社設立日にできます。ただし法務局の休業日は登記申請ができないため、会社設立日にすることもできません。そのため会社設立日の希望がある場合、その日が法務局の休業日に該当しないか確認が必要です。
会社設立日の決め方
会社設立日の決め方に特別なルールはありません。前章で紹介したように法務局へ登記申請を行った日が会社設立日となるため、法務局の営業日であれば好きなタイミングにできます。
会社設立日が事業に与える影響はほとんどありませんが、会社にとって大切な記念日の1つです。また、重要事項でないとはいえ、登記簿謄本に記載される情報でもあります。そのため会社設立日を慎重に決めたいと考える人も多いでしょう。
この章では会社設立日の決め方について、5つの例を紹介します。
縁起の良い日
縁起の良い日は会社設立日として人気のタイミングです。古くからゲン担ぎの意味を込めて、縁起の良い日に何かを始める・縁起の良い日に大切なことをするケースは多くみられます。
会社設立日に適した縁起の良い日の具体例を3つ紹介します。
- 大安
大安とは六曜において「やってはいけないことが何もない日」です。凶とされる時間帯がなく、1日中平穏で大きなトラブルに見舞われない日とされています。
- 一粒万倍日
稲の種である籾1粒から万倍ものお米がとれることから、小さなものが飛躍的に増えるという意味が込められています。会社設立のように、物事をはじめ飛躍を願うのにぴったりの日です。
- 天赦日
日本の暦において最高の吉日とされており、天赦日に始めたことは何事も上手くいくといわれています。
誕生日や記念日
世間一般における特別な日ではなく、自身にとって特別な日である誕生日や記念日に会社設立をするケースも多くみられます。誕生日や記念日は身近なため思い入れが強く、会社設立に対してより一層特別感を持てるかもしれません。
自身ではなく近しい人の誕生日に会社設立をする方法や、一緒に会社を設立する人との間にある記念日に合わせるのも人気の方法です。
ソウルナンバー
ソウルナンバーとは生年月日を足して導き出す数字です。「すべてのものには数字の法則が当てはまる」という数秘術の考えが基になっています。ソウルナンバーを通じて、その人の潜在的な性格や価値観、運命などを考察できるとされています。
ソウルナンバーは生年月日を用いて導くため、その人に割り振られた特別な数字といえるでしょう。ソウルナンバーと会社設立日を合わせるのも1つの手段です。
キリの良い日
縁起の良し悪しや特別な意味のある日ではなく、単純にキリの良い日を会社設立日とするのも人気です。キリの良い日の具体例として、「9月9日」のようなゾロ目や「12月12日」のような月と日が同じになる日が挙げられます。
キリの良い日を会社設立日とする方法には以下のように2つのメリットがあります。
- 見栄えが良い
文字に起こした時の見栄えが良く、ちょっとしたワクワク感や楽しさを味わえるでしょう。このような明るい気持ちは、事業に対する前向きさにもつながります。
- 覚えやすい
キリの良い数字は覚えやすいため、会社設立日に関する質問や会話の中ですぐに答えられます。
他にやるべき作業が少ない時期
会社設立の前後はやるべきことが多く忙しくなりがちです。そのため他にやるべきことがある時期に会社設立をするのはおすすめできません。
特に個人事業主が法人成りをする場合、会社設立は繁忙期を避けて行うのがおすすめです。会社設立後は個人が行っていた事業を会社が引き継ぐ形になります。すなわち、会社設立前後の時期も変わらず事業活動を行う必要があるのです。
繁忙期に会社設立をしてしまうと、本業が忙しい中で会社設立手続きもしなければならず負担が大きくなってしまいます。特定の時期に作業が集中するのを避けるため、会社設立は繁忙期以外のタイミングで行うのが理想です。
ちょっとした節税につながる会社設立日の決め方
節税という面から考えると、会社設立日は毎月1日以外の日が適しています。会社設立日を1日以外の日にすると、初年度の法人住民税が安くなるためです。
法人住民税は法人にかかる地方税の一種であり、以下の要素から成り立っています。
1. 法人税割
法人税額に応じて課税される部分です。法人税額の〇%という形で計算します。
2. 均等割
資本金等の額や従業員数に応じて課税される部分です。
規模に応じて課されるため、赤字・黒字に関係なく発生します。
このうち2の均等割は、事務所を有していた期間が1年に満たない場合は月割りで計算します。計算式は以下の通りです。
均等割の納付額=均等割の年額×事務所を有していた月数÷12
そして、事務所を有していた月数は、1ヶ月に満たない期間は切り捨てとなります。すなわち会社設立日が1日以外、すなわち2日以降であれば、初月は1ヶ月未満となります。したがって、均等割の額が小さくなり、少しではありますが節税につながるのです。
まとめ
会社設立日として登録されるのは法務局へ会社設立の登記申請を行った日です。法務局の営業日であれば、会社設立日を好きなタイミングに合わせることもできます。
会社設立日は特別重要な項目ではありませんが、登記簿謄本に記載される情報の1つです。会社にとって記念すべき日となるため、こだわりを持って会社設立日を決めるのも良いでしょう。