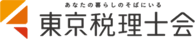ストック・オプション/RSU/ESPPの売却損益計算(総平均法に準ずる方法)
ストック・オプション/RSU/ESPPを売却した場合に、取得時と売却時の差額(株式譲渡損益)の計算をおこなう必要があります。
ここでは、納税額への影響が大きいにもかかわらず、間違えた計算をしている方が多い「総平均法に準ずる方法」について解説します。
ストック・オプション/RSU/ESPPの課税タイミング
ストック・オプション/RSU/ESPPについて、それぞれの課税タイミングは下記のとおりとなります。
このページでは、③の取得した株式の譲渡(Sell)があった場合の株式譲渡損益の計算方法についての詳細を説明します。
- ストック・オプション
① ストックオプションの付与 → 課税なし
② ストックオプションの権利行使 → 給与所得として課税
③ 取得した株式の譲渡(Sell) → 株式譲渡所得として課税
- RSU
① RSUの付与(Grant) → 課税なし
② RSUの制限解除(Vest) → 給与所得として課税
③ 取得した株式の譲渡(Sell) → 株式譲渡所得として課税
- ESPP
① 自社株購入権の付与(Grant) → 課税なし
② 自社株購入権の行使(Purchase)→ 給与所得として課税
③ 取得した株式の譲渡(Sell) → 株式譲渡所得として課税
株式譲渡損益の計算方法
株式譲渡損益の計算は次の計算要素を用い、下記の算式によりおこないます。
株式譲渡損益 = ①△②△③
① 株式の売却金額
その株式をいくらで売却したのか
② 株式の購入(取得)金額
売却した株式をいくらで購入したのか
③ 売却時の手数料
売却に要した手数料
計算用要素のうち、①・③については単純にその年の売却時の金額を使うことができますが、②の株式の購入(取得)金額については注意が必要です。
海外の証券会社(E*TRADE/Morgan Stanley/Fidelity/Charles Schwab/Merrill/UBSなど)では、売却のオーダー時に「昨年VestされたRSUを売却する」「10年前に購入したESPPを売却する」など、売却する株式の取得時期を指定することができます。
この場合、証券会社のレポート上の株式譲渡損益(Capital Gain)は、売却のオーダー時の指定に基づき、②の株式の購入(取得)金額が計算されてしまいます。
ここで申告時に気を付けないといけない点は、この証券会社のレポート上の株式譲渡損益は、日本の所得税法に規定された計算方法ではないため、申告時に使用することができないということです。
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
日本の所得税法では、同一銘柄の株式を複数回にわたって購入(取得)している場合、売却時点で保有している株式の1株当たりの平均購入金額(円ベース)を計算し、これを株式の購入(取得)金額として株式譲渡損益の計算をする必要があります。
たとえば、3年間にわたってVestされたRSUを売却した場合、各Vest時の株価・為替レートを積み上げて計算し、売却直前の1株当たりの平均購入単価と売却金額の比較により利益の計算をおこなうこととなります。
(例)
X1年 100株×100ドル×100円=1,000,000円
X2年 100株×120ドル×110円=1,320,000円
X3年 100株×130ドル×120円=1,560,000円
→ 平均購入単価=(1,000,000円+1,320,000円+1,560,000円)÷(100株+100株+100株)=12,934円
ここで、上記株式を100株売却した場合(@140ドル・130円)、所得税法上の計算方法は下記のとおりとなります。
株式譲渡損益=①△②△③=526,600円(売却益)
① 株式の売却金額 100株×140ドル×130円=1,820,000円
② 株式の購入(取得)金額 @12,934円×100株=1,293,400円
③ 売却時の手数料 省略
仮に、証券会社のレポート上の株式の購入(取得)金額が、X1のものをベースに計算されている場合、株式譲渡損益は、1,820,000円△1,000,000円=820,000円となり、納税額が多すぎる結果となってしまいます。
このように、昨今は外国株式の株高および円安が進んでいますので、証券会社のレポート上の数値をそのまま使ってしまうと思わぬ過大・過少納付が生じてしまうのでご注意いただければと思います。
また、たとえば、RSUのVest、ESPPのPurchaseの2種類の株式増加原因がある場合、RSU分だけで平均購入単価を計算するのではなく、RSU分とESPP分を合算して平均購入単価を計算する必要がある点についてもご留意ください。
なお、配当の再投資も株式増加原因となりますので、配当受領日の数値をもとに計算に加味する必要があります。
まとめ
ここまでの説明のとおり、株式の売却時には、売却した年の情報だけではなく、初めて株式を取得した日から売却時までのすべての情報を保存・整理して株式譲渡損益の計算をおこなう必要があります。
資料がない場合や正しい計算ができない場合には、最悪の場合、取得費の額を売却金額の5%相当額として計算(つまり、売却額の95%が売却益となる)されることとなりますので、ご注意ください。
毎年ご自身で申告・納税をおこなっていたものの、株式譲渡損益の計算が「総平均法に準ずる方法」によっておこなわれてていないことにより税務調査となり、当事務所にご相談に来られるケースも少なくありません。
また、反対に、ご自身での計算が過大納付となっていたため、還付請求(更正の請求)のサポートをさせていただくケースも多くありますが、還付請求(更正の請求)には請求期限がありますので、お早めにご相談ください。
株式の売却をされる際には、今一度正しい計算方法をご確認いただき、過大納付・過少納付とならないようご対応いただければと思います。
お問い合わせ
ストックオプション・RSU・ESPPなどを取得・売却されている場合、できるだけ早くご相談をいただければと思います。まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはフォームからお願いいたします。
【お問い合わせ】
※ 全国・全世界対応可能
※ 守秘義務は厳守します
※ 過去に無申告である場合でも税務署からの指摘前に自主申告できますので、ずっと心に引っかかっている方もご相談をいただければと思います
※ お見積りは、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をご検討いただく方向けに、業務内容の整理を目的として実施しています(申告業務は1年度あたり100,000円~(税抜))
※ 個別具体的なアドバイスをご希望される場合には、タイムチャージでのご相談(20,000円(税抜)/30分)となります
【個別税務相談のご予約】
個別税務相談は、下記より直接日時の予約ができます(クレジットカード決済)